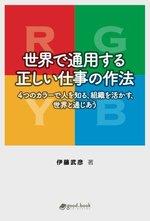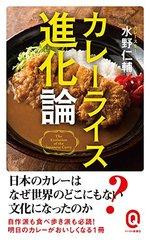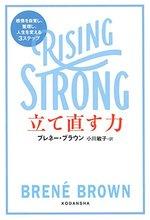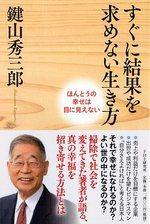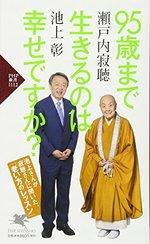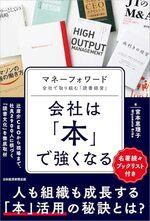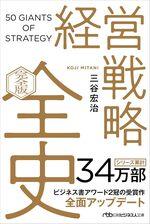「コト消費」の現状
「コト消費」とは
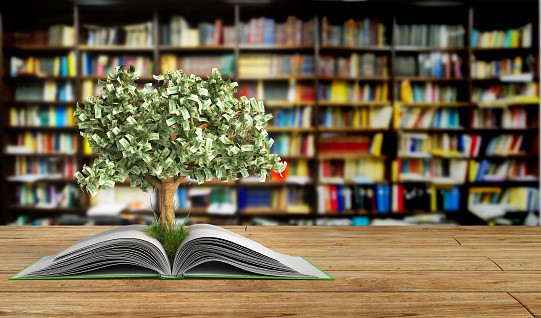
ここ最近、「コト消費」という言葉をよく見かけるようになった。この言葉が流行語になった背景には、これまでのような”モノを所有することに意義を見いだす消費スタイル”が下火になってきたことがある。とりわけ2011年3月の東日本大震災以降、その流れは顕著だ。
それを打開するための手段として、「コト消費」という言葉に注目が集まりはじめた。その象徴的な存在が、2011年12月にオープンした「代官山 蔦屋書店」を中核とする「代官山 T-STYLE」である。これまでの”書店”の概念をくつがえし、本などの「モノ」を売るのではなく、「ライフスタイル」を売り物に定めた。結果的にこの試みは大成功し、流通業界における「コト消費」の流れを決定づけた。
さらに2016年には別の2つの要因も加わった。ひとつは「シェアリングエコノミー」の台頭だ。インターネットを通して、個人同士が空き時間やモノのやり取りをすることが増えた。もうひとつが「爆買い」の終焉である。外国人観光客によるモノの大量消費ブームが過ぎ去り、体験=コトを重視する観光にシフトしてきた。
こうして「体験的価値にお金を払う」という消費の風潮をまとめたのが、「コト消費」という概念なのである。
「コトを売るバカ」になってはならない
「コト消費」はいくつかの種類に分けられる。たとえば純粋に体験=コトそのものが商品になっている場合、それ自体が話題になって売れれば成功となる。
しかし体験=コトでお客さんを誘い、そこで別の商品を売る場合、買い物(モノ消費)につなげられなければ「成功」とはとても言えない。「コト消費」が思ったほどの効果をあげられていないのだとしたら、それはしっかりと「コト」と「モノ」を結びつけられていないからである。これを「コトを売るバカ」と名づけたい。
重要なのは、きちんと「コト」と「モノ」をつなげる消費(=「コトモノ消費」)をつくっていくことだ。単独の「コト」だけでは「モノ」につながらない。売る側だけでなく買う側も「幸せ」になるためには、きちんと「コトモノ」消費にしなければならない。
成功している商店街から学ぶ

どのようにすれば「コト」と「モノ」をうまくつなげることができるのか。2017年夏時点でうまくいっている商店街をひとつ紹介しよう。大阪のミナミ・日本橋(にっぽんばし)近くの「黒門市場(くろもんいちば)」である。
「黒門市場」は、いま成功している商店街の代表格である。江戸時代からの起源をもつ由緒ある商店街で「ミナミの台所」とも呼ばれている市場だ。数年前まではかなり寂れていたのだが、ここ最近は外国人観光客でごった返し、歩くのにも一苦労するほどになった。
黒門市場での観光客は、「食べ歩き」を最大の目的にしている。実際ここでは、買ったものがすぐ食べられるようになっている。店頭では生鮮食品や和牛が焼かれて提供されているし、果物屋も大人気だ。店頭にテーブルが出されていたり、奥に大きなイートインスペースがあったりする店も多い。当然メニューには、中国語や英語も併記されている。Wifi完備の無料休憩所もバッチリだ。
当初は「従来のお客さんに迷惑になる」として、外国人観光客をターゲットにすることについては異論もあったという。しかしせっかく観光客が来てくれるなら徹底的にやろうということで、「黒門市場全体を巨大なフードコートにする」と商店街の組合が合意した。そして各店舗がそれぞれ工夫することにより、口コミで評判が広がって、現在のようなにぎわいのある商店街になったのだ。
もし観光客が増えるという「コト」があったとしても、店主たちが工夫して「モノ」につなげていなかったら、ただ見学するだけに終わってしまい、このような繁盛はなかっただろう。
【必読ポイント!】 「コト」と「モノ」を結びつけるには
商品の説明が案外足りない
体験してもらえればその価値がわかる商品の場合、体験してもらうきっかけをつくることがなによりも大切だ。一方でそうではない商品の場合、「もっときちんと商品の説明をすること」に注力しなければならない。
一般的に「お客さんは商品説明なんて聞きたくない」と思われがちである。しかし意外なことに、お客さんは商品説明を聞きたがっているものなのだ。