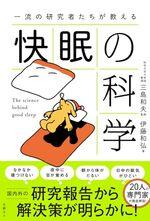私たちはいかにして二足歩行者となったのか
二足歩行は食料探しに有利だった
人間の運動能力はかなりお粗末だ。世界最速のランナーは時速約37キロメートルでダッシュできるが、そのペースは30秒も続かない。チンパンジーであろうとヤギであろうと、多くの哺乳類はその倍のスピードで何分間も軽々と走れる。人間の能力はどうしてこんなにも、地上生活に適応しないものになってしまったのか。
その原因は、人間が立ち上がったことにある。羽をもたず、尾がない生物の二足歩行への進化は、人類以外に例がない。だがその適応は人類にとって有利なものだった。ちょうど人類の系統とチンパンジーの系統が分岐したころ、大規模な気候変動が起こった。このとき効率的に食料を探して手に入れるうえで、直立歩行は有利だったのだ。
狩猟採集をはじめる人類

気候変動によって地球は寒冷化し、それまで類人猿が主食としていた果実は以前ほど豊富でなくなった。
氷河期突入による環境の変化によって、「人間」と呼べる最初の種、ホモ属は進化を遂げることになる。アフリカの開けた場所に住んでいた初期ホモ属は、食べられる植物を探して1日6キロも歩いていたという。だが十分なエネルギーを得るだけの採集ができないことも多かった。食料が激減するなか、初期のホモ属であるホモ・エレクトスは狩猟採集を行ない、食料を確保するようになった。
この頃から女性は子育てをしつつ採集を行ない、男性は採集のかたわら狩猟も行なうという分業体制が確立した。また集団のなかで、食料分配が重要視されるようになった。狩猟採集で得られる植物や肉は消化の悪いものが多かったため、食物の加工も行なわれはじめた。
ホモ属の体はいかにして進化したか
このような狩猟採集生活を経て、人類は長距離移動を行なえる体へと進化し、狩猟のために走ることを覚えた。
長距離を移動するためのもっとも顕著な身体の適応は脚の長さである。典型的なホモ・エレクトスの脚は、アウストラロピテクスの脚よりも10パーセントから20パーセント長い。また武器を投擲するために肩や腰などの身体構造も変化し、肉体の変化とともに腸や脳といった臓器も大きな変化を遂げた。
人間の奇妙な特徴のひとつは、脳と消化管(空腹時)がどちらも重量1キログラムあまりで、同じような大きさをしている点だ。人間と同じくらいの体重をもつ哺乳類の場合、その大半は脳の大きさが人間の約5分の1で、腸の長さは2倍ある。つまり人間は、相対的に小さな腸と大きな脳をもっていることになる。
こうなった大きな要因は、食事と集団生活にあると見られる。道具を使って食料の加工を行なうことで、消化器官への負担が減った。加えて集団生活を行なうにあたり、コミュニケーションをとるための知能が発達したのだ。
ホモ・エレクトスからホモ・サピエンスへ
特殊なエネルギーの使い方

200万年前のホモ・エレクトスの体つきは、首から下を見る限り、現在の私たちの体とほとんど変わらないように思える。しかしよく見ると、彼らがいくつかの重要な点で、大きく違っていることに気づくだろう。