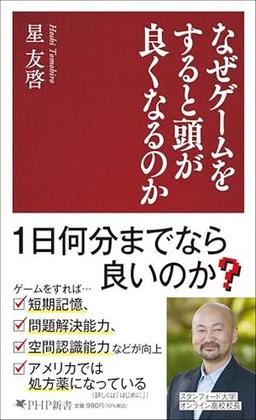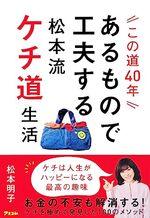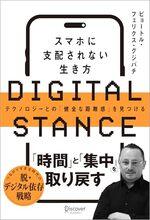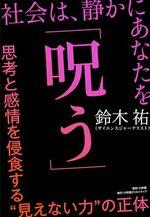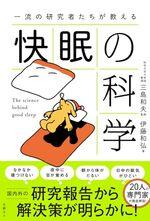できる人こそゲームを楽しんでいる
ゲームは悪影響?
マーク・ザッカーバーグ氏やイーロン・マスク氏のように、世界トップレベルの技術をもつゲーマーで、かつグローバル・ビジネスリーダーである人は少なくない。「ゲームをよくする外科医は、手術ミスが少ない」という研究もあるという。難しく、集中を要するようなゲームが「反射神経や手先の器用さをアップさせる」ことは、科学的に実証されてきたのだ。ほかにも、空間認識能力や注意力、記憶力、視覚的な情報処理速度、マルチタスク能力、クリエイティビティなど、さまざまな認知能力を向上させることがわかっている。「ゲームをプレーすることで、脳自体が変化し、脳の機能がアップする」のである。
とはいえ、これまでは「暴力的になる」「集中力が下がる」といった悪影響ばかりが取り上げられてきたため、にわかには信じがたいという人もいるだろう。このネガティブな影響のほうにも根拠となる科学論文は存在しているが、真逆の結果を示す研究も多い。主に問題となるのは依存症レベルの「やりすぎ」であり、適度であればポジティブな効果だけを享受できるのだ。
ゲームの乗りこなし方、合理的な「攻略法」を身につけることが大切なのである。
ゲームで頭が良くなる

もっとも長く科学的に効果検証されてきたのは、シューティングゲームやアクションゲームだ。これらのゲームは「空間認識能力と注意力を高めてくれる」。意識できる視野を広げ、視覚情報の処理速度を上げるだけでなく、注目すべきポイントへの集中力をアップさせる。
また、「ワーキングメモリーや短期記憶の能力が上がること」も知られている。認識対象を意識にホールドし、適切にコマンドを実行していく。うまくいったプレーを少しの間だけ記憶にとどめ、同じように実行する。そうして難関ステージをクリアしていくことで、認知能力アップのトレーニングを行なえるのだ。
実際、シューティングゲームをよくやっている人の脳をfMRIで可視化してみると、空間全体に注意を向けられていることがわかる。それに、短期記憶を司る海馬の灰白質の増大や、ワーキングメモリーに関わる前頭葉の活性化も見られる。
こうした能力向上に、年齢は関係ない。60歳〜85歳の人たちに12時間のゲームプレーを実践してもらっただけで、20代並みのマルチタスク能力が回復したのみならず、その効果が半年ほど維持されたという研究結果が、世界的な科学論文誌Natureに掲載された。任天堂の「Wii Sports」のように、身体を動かしてバランス感覚や反射能力、歩行スピードを若返らせてくれるものもある。
「ドラゴンクエスト」のようなロールプレイングゲーム(RPG)は、問題解決能力を鍛えてくれる。限られた情報をもとに手もとのツールを駆使して困難な課題を乗り越えたり、異なるタイプの複数のキャラクターを操作して敵を倒したりする。限られたリソースのなかで次々判断を下していくという点で、「テトリス」や「キャンディークラッシュ」のようなパズルゲーム、「信長の野望」のようなストラテジーゲームにも同様の効果が確認されている。
クリエイティブなゲーマー

「スーパーマリオ」のように、多くのゲームは少しずつ難易度が上がっていく設計となっている。そのなかで、ちょうどいいチャレンジを試行錯誤しながら乗り越えていくことで、達成感を得られる。この体験が「成長マインドセット」につながるということが、最近の研究で示された。
成長マインドセットとは、スタンフォード大学教授のキャロル・S・ドゥエックが著書『マインドセット』に書いたコンセプトで、「自分の知性や能力が成長すると考える心構え」を指す。これをもつ人は、新しいことへの挑戦意欲が高く、忍耐強さがあり、批判やミスから学びを得やすいといった特徴がある。
ゲームプレーによって、「自分の能力は変わらない」と考える固定マインドセットから抜け出せるようになるのだ。
そして、ゲームはクリエイティビティも養ってくれることが示唆されている。自由に建物や空間をデザインする「マインクラフト」のようなサンドボックスゲーム、解決法の試行錯誤で想像力をトレーニングできるパズルゲームは、特にその効果が期待できるという。
大勢のプレーヤーとの協力が必要となるMMORPG(大規模多人数同時参加型オンラインRPG)では、学術的にも注目に値するほどの論理的なコミュニケーションがしばしば見られる。データやエビデンスにもとづく説明、相手の意見の展開、効果的な反論といった高次のコミュニケーションスキルは、現代社会でも求められているものだ。
ゲームの都市伝説
暴力性を高める?
ここからは、よくいわれているゲームのネガティブな影響についてピックアップして検討しよう。