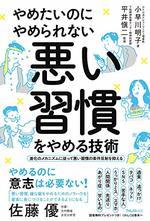「感情」は自分を知るための情報
感情には「理由」と「目的」がある

「感情を抑える」という言い方が一般的であるように、とくに怒りや不安などのネガティブな感情は「コントロールすべきもの」という思い込みが根強い。しかし、ネガティブであれポジティブであれ、感情は何らかの「理由」があって起こるものだ。
自分にとって好ましいことが起こればポジティブな気持ちに、自分にとって不都合なことが起こればネガティブな気持ちになる。感情によって、自分に何が起こっているのかを知ることができるのだ。
また、私たちは無意識の内に、ある「目的」を達成するために感情を利用していることがある。たとえば、子どもが腹を立てたくなるようなことをしでかし、親が怒鳴ったとしよう。しかし、怒鳴る以外の解決方法があるのであれば、怒鳴る必要はない。親は怒りという感情を利用し、怒鳴ることで子どもを黙って従わせているのだ。
このように自分の目的達成のために怒りを利用していると、怒鳴ることが当たり前になっていく。そのうち、まったく腹をたてる必要のない場面においても自動的に「怒鳴る」という方法にスイッチが入ってしまうようになる。
「自分中心」の生き方で感情を味方につける
怒りを相手にぶつけてしまうのは、自分が問題を抱えているからだ。その問題を未解決のまま、怒りだけをコントロールしようとしてもうまくいくはずがない。
怒りが生まれるのは、「他者」を中心とした視点で判断し行動する「他者中心」の考え方をしているからだ。他者に認められたいと願い、必死に行動しても、その欲求が満たされなければ、不満足感が鬱積していく。そんなネガティブな意識がネガティブな感情を生成していき、ついには他者にぶつけないではいられないほど増幅していく。これが「怒り」の正体だ。
著者は独自の視点から、「自分中心」「他者中心」というとらえ方で心のメカニズムを語り、これを総じて「自分中心心理学」と呼んでいる。著者が提案するのは、自分を中心とした視点で判断し行動しようとする「自分中心」の生き方だ。
【必読ポイント!】感情は自分を愛するためのメッセージ
怒りをコントロールするより、原因を突き止める

自分中心的なとらえ方をするのであれば、「怒り」が湧いてくるのは「自分が自分を大事にしていないから」であり、「自分を愛していないから」だ。暴力的な怒りは他者に向かっていても、自分自身を傷つけていると著者は指摘する。