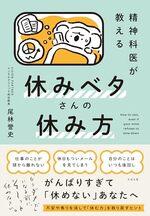なぜ、生きるのがつらいのか
無価値感
「がんばっているのにつらいことが多い」、そう感じる裏には無価値感がある。信頼されたくて人一倍がんばるのは、自分を特別な存在として見てもらいたいからだ。「優劣が自分の存在価値に直結」すれば、相手を称えるよりうらやむ気持ちのほうが強くなり、自分の写った写真すら否定したくなる。
人はその成長過程において、「多かれ少なかれ本来の自分を抑えて周囲に適応し、周囲の気に入られるように自分を形成する」。これを本書では代償的自己という。代償的自己は自分の感情よりも周囲の要望を優先するため、無価値感の強い人はより強固な代償的自己をつくりあげる。自分を貶めて場違いな笑いをとろうとしたり、卑屈なまでに相手の好意を過大評価したりする。他者に支配、利用されやすく、屈辱感を抱えがちで、必要以上に傷つきがちだ。自信がないために引っ込み思案になり、積極的なグループ参加ができない。
そうして無価値感が強いと、心身につねに負担を抱え込んでしまう。消極性のせいで気分転換もうまくできず、結果として自律神経系などのバランスが崩れて体調不良に悩まされる。
「自分に価値がある」ということ

人と比べて未熟なところがあっても、「自分には無条件に価値があるという感覚」を自己価値感という。温かな愛情、人として尊重されること、大きな仕事の完遂といったことを体験するときに、幸福感などとあわせて感じることができる。
心の深層にある基底的自己価値感と、表層にある状況的自己価値感は区別しなくてはならない。表層の自己価値感を肥大化させることで、基底にある無価値感を補おうとしている場合が多いからだ。
基底的自己価値感は、児童期の中頃には確立してしまうとされている。これは、「愛情豊かで適切な養育環境」において形成され、3つの条件を満たすことが必要だ。「子どもが安心を得ていること」、「子どもが(外界に対して)適合性の感覚を得ていること」、「無条件に親から歓迎されているという実感を得ていること」の3つである。この自己価値感をしっかりと持っていれば、自分と他者を信頼し、外界に対して能動的に働きかける適応能力を発達させられる。
一方、状況的自己価値感は、老年期まで形成と変容が起こる。その形成要因は次の3つである。まずは他者との交流だ。受容される体験は自己価値感を高める。深く心が通じ合う友情との出会いなどが、基底的無価値感を修復することもある。次に、他者から寄せられる評価だ。注目されたり尊敬されたりすることを誰もが求めている。3つめは、自分の力の拡大の自覚だ。身体が魅力的になる、能力が高まる、成功、競争での勝利といったことが自信をもたらす。
より自己価値を向上させるために、これらの達成に向けて努力する。そうして「自己価値感の源泉がバランスよく機能すれば、健全で安定した自我がもたらされる」のである。
基本的な欲求である自己価値感欲求が満たされないと、強迫的に執着するようになる。基底的無価値感の強い人は、誰からも称賛され、愛されることを望み、それがゆえに自己犠牲的になってしまうことがある。そうして、医療や福祉などの分野で尊敬される生き方をする人もいる。そのための能力や環境が整わない場合、自己価値感欲求は、努力の放棄や強情、幼稚な甘えといった屈折したかたちであらわれてしまう。思春期以降では、そのように自己否定的な方法で無価値感を埋めようとしがちだ。
大人に無価値感をもたらすもの

思春期以降のどのような体験が自己価値感を揺り動かし、状況的無価値感を生み出すのか。本書で紹介されているものから、いくつかピックアップしてみよう。