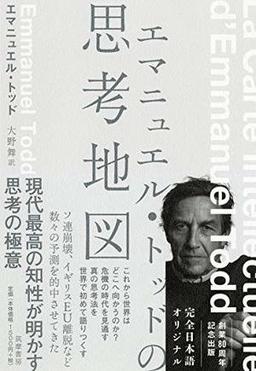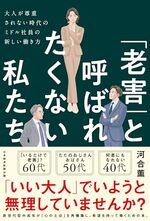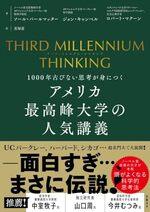【必読ポイント!】 膨大なデータの蓄積が思考を支える
知らないことを知る感動こそ思考の神髄
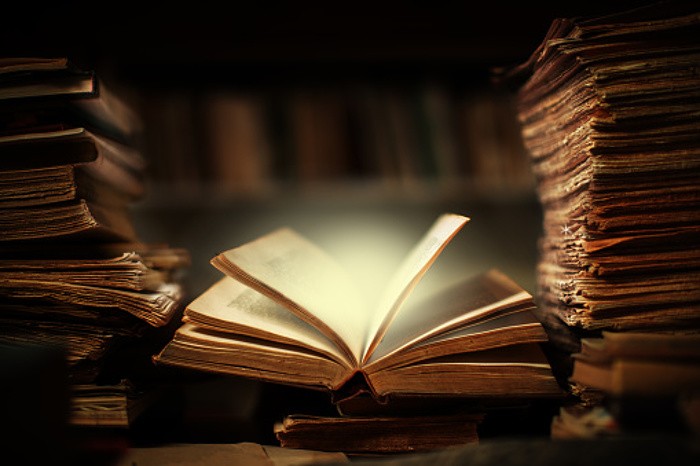
思考とは何か――。プラトンら哲学者たちは古来その答えを探究してきた。しかし著者はそうした抽象的な問いと一線を画し、思考することは着想などの自然発生的に起こるメカニズムだと捉えている。
思考という行為の前に、まず学ぶという行為がある。著者にとって学びの大半を読書が占める。自身が専門とする歴史人口学に限らず、幅広い文献を読み漁ってきた。大量に読んで学び、知らないことを知ったときに感動する。それこそが思考するということでもある。
思考そのものはとっさの行為、「思いつき」や「気づき」のような着想である。着想自体の当否を検証するうえで重要な役割を果たすのが、統計学や歴史学といった学術的なフレームだ。
こうした知的活動に必要な知性は大きく三つに分けられる。それは頭の回転の速さ、記憶力、創造的知性である。頭の回転の速さと高い記憶力による知的処理は、思考を必要としない。いわばテクニックだ。一方、創造的知性とは、脳内のさまざまな要素を自由に組み合わせ、関連づけることができる知性を指す。これこそが斬新なアイデアを思いつくために不可欠なものである。
最重要は入力=データの蓄積
あらゆる知的活動は、「入力(インプット)→思考→出力(アウトプット)」の3フェーズから成る。「入力」は読書や統計の読み込みを通じたデータの蓄積を指す。「思考」は着想(仮説)、モデル化とその検証、分析を含む。そして「出力」は執筆や発言を通じた成果の発信を意味する。
一連の知的活動のうち、最重要かつ著者にとって最も面白い作業は入力である。
無我夢中で本を読み、知識を蓄積していく。すると、ある時点で脳がデータバンクのようになり、やがてある思考モデルが立ち現れる。その境地に至る過程はさながら、探偵小説『アルセーヌ・ルパン』の一節「まだ十分に材料が揃っていない。考える前に進まなければならない」という状況のようだ。波乱万丈の冒険を通じて材料=データを集めるルパンが、旅するように文献を読み漁る著者の姿に重なる。
データ蓄積に関連して、著者は独自の読書術を紹介している。まず本の大切な箇所のページ数とコメントを、表紙の裏から最初の数ページにある空白に直接書き込む。