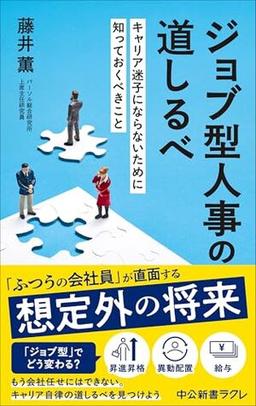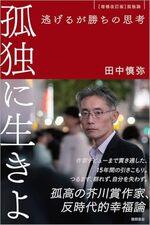ジョブ型について企業が考えていること
6割以上の企業が「ジョブ型」や「職務給」に前向き
日立製作所、KDDI、富士通など、名だたる大企業で「ジョブ型人事制度」や「職務給」の導入が相次いでいる。諸調査によると、ジョブ型人事を導入済み、もしくは検討中である企業はおよそ6割。職務給の導入状況に至っては、管理職層で職務給や役割給を導入している企業が70%、一般社員でも50%に上る。
人事制度や給与制度には「ヒト」基準のものと「仕事」基準のものがある。「ヒト」基準は、その「ヒト」の能力や経歴などに応じて等級や給与を決めるやり方で、職能等級や職能給、年齢給などがそれにあたる。
一方の「仕事」基準は、誰が担当するかに関係なく、「仕事」そのものに応じて等級や給与を決めるやり方だ。職務等級や職務給、役職手当、役割等級、役割給などが「仕事」基準である。
企業がジョブ型や職務給を推進する理由

ジョブ型人事や職務給に関心をもつ企業がなぜ多いのか。それには2つの理由が考えられる。
まず、「人件費の合理性」を高めるためである。仕事と処遇の関係を見直し、仕事に応じて給与を決めたい、つまり、職務給の導入を図りたいのだ。
仕事と処遇の関係で、矛盾が目立つのが管理職層である。多くの日本企業は能力主義の等級制度である職能資格制度を導入してきたが、等級別の定員がなく、しかも一旦昇格すると降格しない。そのため、たとえば課長相当の等級に実際の課長だけでなく、ポストについていない実力の怪しい人も在級してしまう。在級年数が長いと定期昇給が積み上がり、その等級に付随する職能給の上限まで近づく。結果、企業にとっては課長ではない人にも課長と同程度か、それ以上の給与を支払うことになってしまうのだ。
2つめは、「タレントマネジメント実践」のためである。タレントマネジメントとは、「経営戦略推進に向けて、各ポジションに最適なタレント(才能)を確保するマネジメント施策」を指す。次世代マネジメント人材の発掘や、競争の激しいIT人材の確保などもこれにあたる。エンジニアなど、需給タイトな職種の人材を獲得するためには、ジョブ型や職務給で対応する必要が高まっているのである。