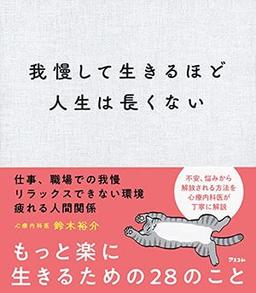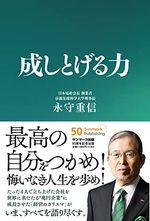他人による境界線侵害「ラインオーバー」
「自分らしい人生」を取り戻すには
「いい学校・いい会社に入って、不自由のない暮らしをするのが勝ち組」「結婚して子どもを育ててこそ一人前」……。私たちは日々、他人が考えた価値観やルールを一方的に押しつけられ、自分らしさを否定されている。心身が悲鳴を上げても「親が言うから」「常識だから」と受け入れてしまい、我慢を強いられていることに気づくことすらできない人もいるだろう。
「自分らしい人生」を取り戻すには、人間関係のあり方を見つめ直すことが必要だ。他人のルールに縛られずに生きるためには、その人間関係が「好ましいもの」であるかどうかを、しっかり見極めなければならない。
好ましい人間関係は、公平(フェア)で穏やかだ。価値観を押しつけられることも、ミスや欠点を過剰に責められることもない。「自分は自分のままいて良いのだ」と感じられ、心が安定する。一方、好ましくない人間関係は、他人のルールであなたを縛りつけ、時間やエネルギーを奪い続ける。こうした関係の比重が高いと自分らしく生きられず、日々の生活に喜びを感じられなくなる。「自分は何をやってもダメだ」と絶望感や虚無感に襲われることもあるだろう。
自分と他人の間の境界線を守る

好ましい人間関係を増やしていくために心がけたいのは「自分と他人の間の境界線を意識して、守る」ことである。世界には、「自分が責任持って守るべき領域」と、「他人が責任持って守るべき領域」がある。自分の心や身体、生活、人生は、あなたが守るべき領域だ。もちろん人間は一人で生きていけないから、他人の力を借りることもあるだろう。しかし、責任やコントロール権を他人に委ねてはいけない。一方、他人の心身や人生は、その人自身が責任を持たなければならない「他人が責任持って守るべき領域」だ。家族や友人など、どんなに親しい間柄であってもそれは変わらない。
しかし、実際には境界線侵害(ラインオーバー)が頻繁に起きている。