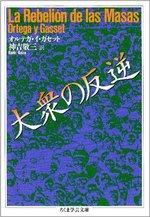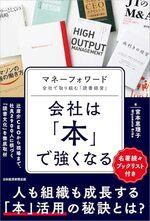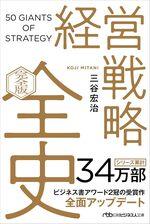【必読ポイント!】 ポスト・パンデミックの世界
倫理的進歩に向けて

COVID―19の蔓延によって、人類史上初めて、世界中の人々の行動が「同期化」した。人々が同時に同じ行動をとったのである。コロナ禍によって民主主義における統治のシステムとリーダーシップの重要性がよりはっきりした。このウイルスが消滅する可能性が非常に低いという事実を見ても、世界が以前の「普通」に戻ることはできないことが予想される。
著者は「危機は倫理的進歩をもたらす」と考える。倫理とは、文化によって異なることのない、普遍的な価値のことだ。人体が脅かされるのを防ごうとするのは、極めて倫理的な行動だ。パンデミックの最中に様々な倫理的問題が議論されてきている。
一方で、我々は史上最大の経済危機を目前にしており、経済問題と環境問題にどう倫理的に対処するかを議論しなければならない。経済と倫理は相反するものだと思われがちであるが、これはマルクス主義的な誤解だ。資本主義のインフラを使って、失業者雇用や環境保全などの倫理的に正しい行動をとること、「ネイチャー・ポジティブ」な経済は実現可能である。
倫理的価値体系と経済的価値体系を一致させることを、著者は「善の収益化」と呼ぶ。現在の問題は、市場経済は搾取によって成立するという誤った考えに基づいて生じたものだ。儲けるために搾取をしなければならないシステムは間違っている。現在直面している経済危機は、過去の非倫理的な行動の結果だ。倫理的に正しい行動をとった結果、経済的に儲かる経済体制を作るべきだ。
ネオリベラリズムの終焉
世界経済フォーラムのクラウス・シュワブらによる『グレート・リセット』では、ネオリベラリズムが終焉すると書かれている。著者の考えも同様だ。ネオリベラリズムの秩序はグローバリゼーションの一つの解釈だ。人間は基本的に利益に関心があり、可能な限りの利益を手に入れようとするのが合理的であるという考えに基づき、新自由主義経済論的な市場経済を前提とする。人類はグローバルな空間で財を交換するようになり、グローバリゼーションは自由と民主主義をもたらすと考えたが、世界史的に考えればそれは誤りだ。戦争、中国やロシアの台頭、そしてウイルス。パンデミックとの闘いでグローバリゼーションがもたらした富は消え去り、環境に甚大な被害を与えたことを加味すれば、残った財産はむしろマイナスである。このようなシステムに固執する必要はない。新しい経済モデルや、新しいグローバリゼーションの捉え方が必要だ。
普遍的な倫理に基づいて行動するために、人類には連携が求められているが、実際には多くの分断が生まれている。グローバルな協力体制は、普遍的な倫理観に基づくものでなければならない。例えば日本とEUがアフリカを対等なパートナーとして捉えるアフリカ戦略を作れば、これまでとは異なる協力関係が生まれるかもしれない。哲学者のデリダのいうところの「友愛のポリティクス」のように、国際協調は普遍的な倫理観に基づいたものであるべきなのだ。
統計的世界観

現在、メディアは毎日感染者数を発表しているが、ジャーナリストはデータの専門家ではないし、大衆もどんな情報を与えられているかわかっていない。刻々と変わる統計を見せるのは、誤解を生み、不安を煽るだけだ。我々は普段統計を見るのに慣れ過ぎている。
ドイツも日本もGDPの成長率が中国よりも低い。私たちが中国のGDP成長率を見て思い描くのは、猛烈な勢いで進展する光景であるが、中国は共産党独裁体制下にあり、北京は深刻な大気汚染に悩まされている。GDPよりも、街のきれいさ、自由な社会、食べ物や空気の質の方がよっぽど重要だ。
問題は数字ではなく、質だ。だからこそ著者は、質的・倫理的経験や感情に焦点を当てて、ウイルスに対する見方を変えようと試みている。
この危機を超えた後、著者が思い描くのは環境への配慮が行き届き、技術的に進んだ世界だ。人々が非倫理的な行動をとる原因の多くは、恐怖である。ビジネスで非倫理的な行動をとるのは、競争相手に負けることや、収入を失うことを恐れるからだ。自分や家族を守ろうとするのは自然な気持ちだ。そもそも、基本的人権である生命を失う恐れはあってはならない。
著者は前著で、ヘーゲルが「人倫」=ジットリッヒカイトと呼んだ倫理的な社会が必要だと主張した。その実現のためには「あらゆる人が、貧困のラインを越える基本となる最低限の所得を得る必要」があり、「完全な持続可能性」が求められるとした。これは共産主義ではなく、持続可能な資本主義だ。
国と国のつながり
トランプと陰謀論

アメリカではQアノンという陰謀論が流布された。ドイツではあるエリート集団が民主主義を破壊するためにウイルスを製造したと主張する“Querdenker” という集団がいる。ある調査によればドイツ人の37%が「パンデミックは実在しない」と考えている人を少なくとも一人は知っているという。陰謀論が増殖した背景には、ロックダウンで人々が家に閉じこもり、妄想を巡らせたことがあるのではないかと著者は語る。
陰謀論が消えないのは、メディアの偏向報道にも原因がある。ほぼ全世界において、ドナルド・トランプは批判的な報道をされてきた。ドイツのメディアは、トランプが対策を誤ったために、アメリカでのパンデミックがとりわけ拡大したと報道した。しかし、実際の対策を行なったのは各州の政府だ。最大の被害を受けたニューヨーク州は民主党が支配しており、共和党のトランプが大統領であったためにパンデミックが深刻化したというのはフェイクニュースである。
バイデンが当選してもなお、ドイツでの陰謀論の数は増えていることから、トランプとドイツにおける陰謀論の数に関係はないといえる。陰謀論は、ソーシャルメディアを含むメディア全体の構造と関係がある。人々は、ある動画が1000万回再生されたら、その人には影響力があると勘違いする。その人はYouTube上で影響力があるかもしれないが、実社会でも影響力があるとは限らない。メディアは虚構ではなく、事実を報道すべきだ。
人種差別とステレオタイプ思考
パンデミックによって世界で人種差別による分極化が進んでいる。人種差別主義は、倫理的価値を否定する根本的に間違った考えだ。問題の本質は、ステレオタイプ思考にある。ステレオタイプ思考は、一つひとつの行動をきちんと説明する代わりに、固定観念で全て片付けようとする。例えば、著者は2人の日本人インタビュアーが正しい茶碗の持ち方をしているのを日本人らしい行動として印象的に感じていた。しかし、同じ日本人で、同じ行動をとっていても、その行動をする理由はそれぞれ異なる。ある人の行動を「個人の行動」と捉えずに、「日本人一般に共通の行動」と捉えるのは間違いだ。そのような解釈では、相手と交流するのではなく相手の表象と交流することになってしまう。それは、相手を真の意味で尊敬していないことを意味する。
アメリカのソフトパワーは強力であり続けたが、それはアメリカ産の靴やジーンズ、映画の品質が優れていたために、人の心を支配できたからだ。しかし、現在はソーシャルメディアやグーグルなどのサーチエンジンが侵略的な監視システムとして人々を支配しようとしているとして、批判が強まっている。著者の考える一番良いソフトパワー、すなわち地政学的戦略は、同盟国を作ることだ。反アメリカ的なデジタル戦略を検討しているEUは、環境に配慮し、内省し、礼儀正しい、優しい国になろうとしている。真のソフトパワーは敬意と信頼だ。
他者とのつながり
ソーシャルメディア
グーグルのサーチエンジンは、人の検索行動を利用してその人の行動を操作し、長い間オンラインに止まらせようとする。この点は、すべてのソーシャルメディアも同様だ。異なる意見を提示した上で、合意点を得ようと倫理的な討論は、ソーシャルメディアでは機能しない。そのため、ネット上での中傷には自己防衛の手段がない。これは、とりわけソーシャルメディアを過剰に利用する若者たちに深刻な影響を及ぼすことになる。アメリカのソーシャルメディアは、自由民主主義を破壊するドラッグだとすらいえるだろう。
人の行動を変えるソーシャルメディアは、我々に自己を与える。ソーシャルメディアは本人が望んでいない、もともと持っていなかったアイデンティティを押し付ける。「アフリカ系アメリカ人」「白人」「左翼」「右翼」「若い」「歳をとっている」といった、本来は幻想に過ぎないアイデンティティを押し付けられると、人は誤った自己概念に基づいて行動するようになる。著者は「確固たる自己がある」という考えを捨てることが自己を見つけることだといった仏教の考えを支持し、人間は複雑なプロセスの塊であると指摘する。
日本人のコミュニケーション

アジア人は共同体を尊重するというステレオタイプに反して、日本は先進国の中で最も社会的に孤立しているというデータがある。著者によれば、日本はドイツよりもデジタルな交流が普及していて、デジタルなインフラに対する批判も少ない。2012年に来日した著者は、人が携帯電話に支配され、行動を統制されている「サイバー独裁」の国だと感じたという。日本人は、意見の対立を避けようとするよりも、むしろ対立を増やし、対立にさらされる機会をつくるべきだ。そしてしっかりとディベートを行う。ユルゲン・ハーバーマスの社会論が提案するように、「冷静にディベートをしたかったら、ディベートの時間・空間をきちんと設定」すべきだ。相反する信念を持った二人が、どちらが正しいか決める、あるいは妥協点を探りながらより良いシステムを構築するために、ディベートは行われるべきだ。
個人の生
人生とは何か
最後に、著者が「新実存主義」と呼ぶ立場に基づき、人類とは何かについて考える。人間は自分は何者かという認識に基づいて行動する動物である。動物はただ動物であるが、人間は自らが動物であることを問題視する。著者が考える人生の意味とは、「生きること」だ。しかし、すべての人生が良い人生とはいえない。健康にめぐまれ、ささやかな幸せの詰まった一日を過ごすことができれば、そこには価値がある。
人生の意味は、自分のライフライン=命綱を見つける能力にかかっている。自分が幸せになれるゾーンは人によって異なる。これを見つけられれば、それは自分の運命であり、その運命が幸せをもたらすのである。
著者は、人類により理性的な行動を求める。理性的な行動とは、統計的世界観とは異なり「なにゆえにこうあるか」という「理由律」に従って行動することである。「考える」とは正しいか正しくないかわからない物事を把握することである。真実と虚構の違いは、思考があるところにしか存在しない。人は考えることで現実を「把握する」のである。
それに加えて、人が生きていることを実感するには美的体験が必要だ。芸術や美味しい食事などの心地よい経験を、できるだけ多く人と共有しよう。芸術に触れることは、人類の進歩にとって重要な役割を果たすであろう。</p>